-1024x576.png)
第6回 のドネーション交流会のゲストは
KYOTO学防災(まなぼうさい)の星千春さん
星さんは、東日本大震災のときに福島で被災され
その経験をもとに、京都に移り住まれた現在は
ご夫婦で防災に関する啓発活動、各種イベントなどを開催されいています。
合言葉は「地域力は防災力」
備えといってもいろいろあるけれど
いざというときに一番力になるのは人との繋がりの力
詳細はInstagramをご覧ください。

“知る”から始まる“備え”と、人とのつながり
今回の会ドネーション交流会では、
各地で起きた災害のリアルな経験をもとに、
「私たちにできる備えとは何か」 を
参加者みんなで考える時間となりました。
「備え」と聞くと特別なことのように思えますが、
実際の災害現場では、訓練していても咄嗟にヘルメットすらかぶれない。
雪の中で動く余裕さえなくなる。
そんなリアルが共有されました。
福島では原発が注目されがちですが、
内陸部での被災も深刻だったこと。
熊本では、障害のある方たちの受け入れ先が見つからない問題、
介護職・看護師の不足、
福祉避難所の人手不足など、
災害は“社会の弱い部分”に一気に押し寄せる ことも語られました。
災害が怖いのは、知らないから。
でも、知ることでできる備えは確実に増えていきます。
たとえば…
- 子どもの年齢によって必要な備えが変わる
- 先生たちだけで子どもを守りきれるのか? 地域の力が必要
- 小中高で避難マニュアルは違う。自分の学校の対応を要確認
- 避難所の班分けにどんな役割があるのか
- 水問題(長時間並ぶ・子連れで大変・並んでも飲めないケース)
- マンホールトイレは、おもりや付属品など“実際に使って分かる必需品”が多い など
そして何より、
被災者同士が助け合う力が、災害後の大きな支えになる
という話に、みなさん深くうなずいていました。
そして、災害の現場を知る人たちからは
災害が起こった時は、まず、命を守ることが最優先であることも語られました。
命があって初めて、備えが活かされる時が来る。
そして「生き延びる力」が必要になってくる。
災害対策は、一度学べば終わりではなく、
子育ての時期、介護の時期、年齢によって
“アップデートし続けるもの” だということも学びました。
大切なことをたくさん教えていただく時間でした。
今回の学びが、
「怖いから見ない」ではなく、
“知ることで守れる命がある”
そんな前向きな一歩につながることを願っています。
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
参加者の声
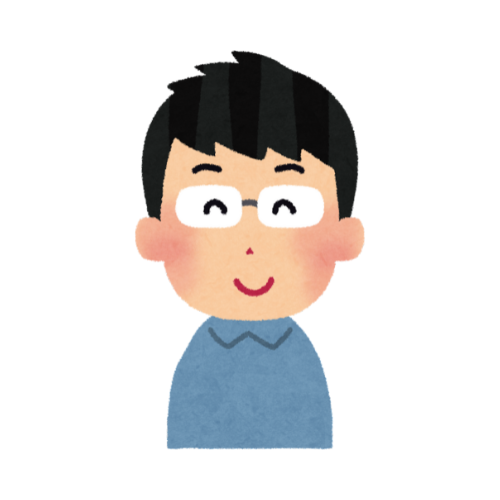
普段から気になってはいましたが、
改めて地域の繋がりが大事やなと思いました。いろんな視点で備えます。ありがとうございます。



日常での地域のつながりが、災害時に生きてくると改めて知りました。
被災者が指揮をとって、避難所を運営することを知らない人も多いと思うので、地域での自助と共助の研修をして欲しいと思いました。



日常において「防災」について考える機会を増やすことが、少しずつ防災対策を充実させることにつながると思いました。



普段困ってない時は気にも留めていない方が殆どで、その時になって初めて備えが必要だったと気付く。
それを知っている者として、伝えていくこと、その時個々にどうするのか、やはり普段から語り合える環境が必要だなぁと感じました!
貴重なお話ありがとうございました。
収支報告
- 収入合計 55,000円
・参加費+会場の立ち縁り様、参加者の皆様からの寄付 - 支出合計 40,000円
・食事代、会場代 - 寄付金額 15,000円
次回のご案内
次回は、第7回は2026年1月24日(土曜日)、
寄付先は合同会社セブンスターズさんです。
合同会社セブンスターズさんは、
困難を抱える若者の自立を支援するシェアハウスを運営。
住宅提供にとどまらず、生活・就労支援を行い、
行政やNPOと連携しながら社会とのつながりを築く場を提供しています。
また、児童養護施設の退所者向けに「一人暮らし体験施設」も展開し、
自立への第一歩を後押しされています。
当日は、代表の田代貴之さんにご登壇いただきます。
お楽しみに!
-1-724x1024.png)
-1-724x1024.png)

.png)
コメント