「こずえのつぼみ」代表の神野が、有料の相談窓口や申請代行業などを使わず、NPO法人化のために、実際に取り組んだ内容を記した奮闘記(その2)。
今回は登記に必要な書類準備で苦労したことや、注意すべき点などを綴ります。
- NPO法人設立の申請に必要な書類一覧
- 特に書くのに苦労した「設立趣旨書」と「定款」について
- 書類準備での注意点
- これからNPO法人を作ろうとする方へのメッセージ
大阪市の窓口とのやり取りなどを記載した前回の記事はこちら↓

NPO法人設立の申請に必要な書類一覧
NPO法人設立の申請には、下記の11種類の申請書類の作成が必要となる。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿
- 各役員の就任承諾及び誓約書
- 役員の住所または居所を証する書面
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
- 確認書
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立の初年及び翌年の事業計画書
- 設立の初年及び翌年の活動予算書
ほとんどの書類は決まった様式があったり、調べれば書き方がわかったりする。
一方、この中でも、8「設立趣旨書」は書式がなく、自分たちの言葉での発信が必要となり、
2「定款」はボリュームが多いため、書くのが大変だった。
そのため、今回、神野がどのような点に注意して書いていったかを記録していく。
設立趣旨書
沢山の申請書の中で、書式が無く自分たちの言葉で発信するのが、この「設立趣旨書」になる。
「設立趣旨書」には大きく2つの項目で記載しなければならない。
①趣旨、②設立に至るまでの経過、である。
趣旨
「趣旨」については、自分たちがNPO法人を作ろうと思った理由となる。
最後に「〇〇を目的とします。」という文言で締めくくると分かりやすいかもしれない。
この部分は定款や申請書にも流用できるので、短く簡潔に書いておきたい。
設立に至るまでの経過
「設立に至るまでの経過」については、設立に至った背景にあるもの。
「こずえのつぼみ」の場合だと、不登校問題の深刻化に、シングル家庭の増加と不登校の関係性、加えて発達障害やグレーゾーンと言われる子供たちの増加など、参考となる数字を示し、その支援が必要であるという経過(背景)を記載している。
もし、設立前にすでに活動しており、その活動の内容や成果を上げられるなら具体的で伝わりやすいかもしれない。
定款
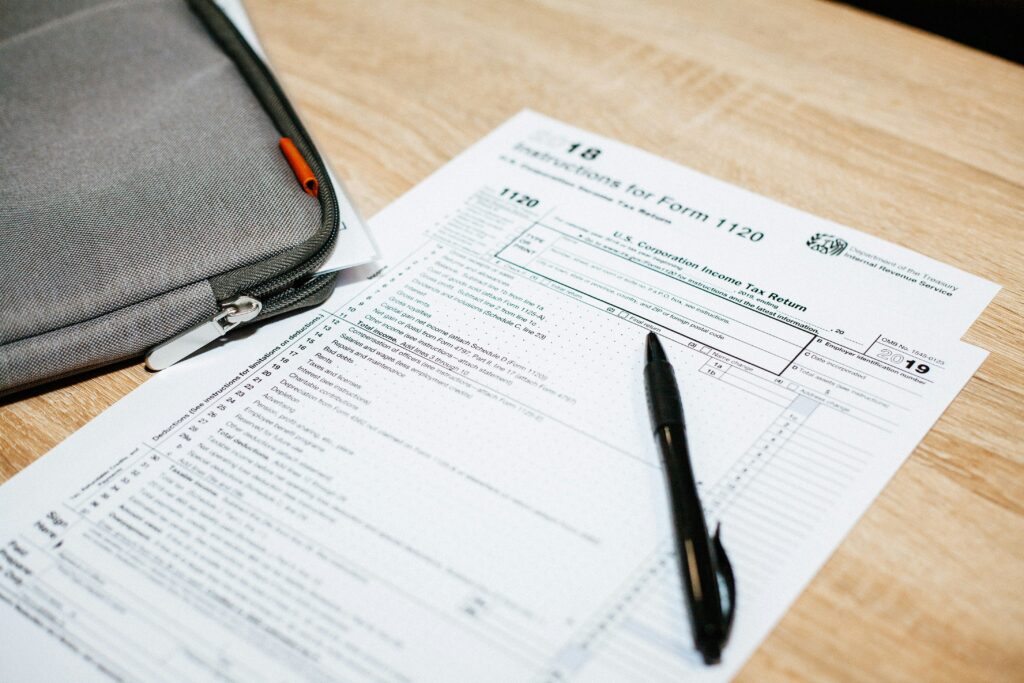
定款は各市によって微妙に違いがあるものの、概ね書き方や書式は同じと思ってもよい。
大阪市の場合だと第10章 54条までの項目があるが、その大半はほぼ書式通りに記載することになるので、ボリュームに圧倒されず丁寧に書いていきたい。
目的及び事業定款
目的及び事業定款ではまず「目的及び事業」の項目。先ほど「趣旨書」で述べた「①趣旨」をそのまま流用すればよい。
特定非営利活動の種類
これは行政が示す20項目から自分たちの事業がどれに該当するかを選んで記載する。
定款は頻繁に記載変更できないという理由で、沢山書いた場合でも、行政または担当者によってはその根拠の明示まで求められるため、設立初年度に関しては明らかに合致する活動のみ記載することをお勧めする。
事業
「事業」に関しては、(1)特定非営利に関わる事業 と(2)その他事業の二つがある。
(1)特定非営利に関わる事業
これは主たるNPO活動となるが、基本的に利益が発生しない事業の事。
(2)その他事業
「(2)その他事業」こちらは利益が発生する事業。NPO活動において、活動する人たちや資材の購入など事業である以上人件費や経費が発生する。
そこを補うための利益活動は当然認められており、そこを補うのがこの「その他事業」となる。
NPOによっては「その他事業」が無く、いわゆるトントンで終わらせている場合や、持ち出しを常態化している場合も見受けられる。
しかし事業である以上助成金のみに頼らず、自ら事業を起こしたり、寄付を募ったり、NPO法人としての独立採算を確立するべきだと思う。
そうでなければそもそも事業として成り立っていないので、いずれ立ち行かなくなるのではないか、とも感じる。
会員
「会員」の設定は各NPOによって任意の設定となる。これは会費(収入源ともなる)と連動するためしっかりと構築する必要がある。
役員及び職員理事
役員及び職員理事は3人が最低限必要となる。
しかし、配偶者や3親等以内の身内がいる場合は、総数が3分の1を超えてはならないという規定がある。
要するに、身内だけで議決権の3分の2を握ってしまい、実質の支配権を行使できてしまう組織ではいけないと言う事。
もし夫婦で理事をやる場合は、その他に4人の理事を設定し合計6人にして、夫婦の議決権を3分の1にしなければならない。
監事
監事は独立した1名を設定しなければならない。
社員総数で10名という規定の中に理事も監事も含まれてはいるが、監事は報酬を得ることが出来ず、職員を兼ねることは出来ない。
理事の報酬
これは総数の3分の1の範囲で報酬を受け取ることが出来る。
つまり3人いれば1人だけが理事としての報酬を受け取れる。
これは現実的に理事間での納得感やコンセンサスが重要かも知れないが、理事全員が職員として働いている場合であれば、理事全員が役員報酬を設定せず、職務において発生した給料を受け取ることも検討できる。
役員報酬は株式会社と同じで一度決めると年度内は変更できない。
また、ここで多額の報酬を受け取っていると、NPOの場合信用力にも影響がある。日本では非営利活動法人(NPO法人)=ボランティア のようなイメージが強いことと、逆手にとって悪用する組織も存在したため、その透明性を問われる場合もある。
附則
この項目は定款の最後の項目になるが、実際の理事、監事の氏名や各会員の入会金などの記載が必要となる。
入会金は、会員ごとに設定でき、金額も0円~ いくらでも設定は可能だ。
年会費だけでなく、月額の設定をする場合でも、それを記載すればよい。
ここで注意したいのは、流動的な「その他事業」はここでは触れられないこと。
活動を維持するための資金源としても収入と支出の整合性を考えながら設定したい。
最後に

NPO法人に関するあり方や考え方は欧米とは異なり、日本では無私の奉仕的なイメージが強い。
しかし、法人組織であり申請後には法務局で法人登記をして税務署に税金を納めることになるのだから、独立採算が出来る活動をしっかりと考えたい。
奉仕的な理念(ベネフィット)と維持運営するための利益(プロフィット)は両輪でなければならない。
理想的な目的に向かっていくためにも、これからNPO法人を作ろうとする方たちには独立採算をしっかりと考えてもらいたい。
現状、実質活動休止中のNPO法人は相当数に上っている。
ボランティアの延長で法人化したNPO団体は法人としての責任を軽く見ている場合が多いように感じる。
法人として維持発展するための利益は最低限必要であり、NPOだから稼いではいけない、などというのは全くの幻想である。
NPO法人の在り方や活動方針、利用者の適切な利潤を追求するためにも、維持発展をしていきたい。
(参考:内閣府NPOホームページ)
続きの記事はこちら↓

